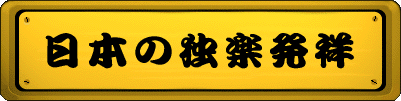日本の独楽の歴史についてひもといてみると「こま」の由来は「高麗(こま)(朝鮮)」に通じ、中国から朝鮮を経由して渡来してきたのが始まりというのが通説です。しかし、本当に朝鮮から渡来したことによって日本の独楽の歴史は始まったのでしょうか。 日本の独楽の歴史についてひもといてみると「こま」の由来は「高麗(こま)(朝鮮)」に通じ、中国から朝鮮を経由して渡来してきたのが始まりというのが通説です。しかし、本当に朝鮮から渡来したことによって日本の独楽の歴史は始まったのでしょうか。
 このホームページの「こまの歴史」に引用した中田幸平も述べているように、日本で「こま」という名が残っている最も古い文献は「和名抄(わみょうしょう)」です。和名抄は「和名類聚抄」の略です。これは平安の中期、931〜938年にかけて編纂された和漢辞典で、分類した漢字の和名を万葉仮名で注釈したものです。その中で「独楽」の項目は鞠や双六と同じ「雑芸具」に分類され、「古末都玖利(こまつぐり)」と記されています。和名抄の「独楽」には「孔があいている」という解説がある事から、今でいう「鳴り独楽」のように空洞が空いているコマが朝鮮から伝来したものと思われます。また、和名抄の分類を見ると独楽は雑芸具(遊具)の部に入っています。遊具であれば宮廷人の中に止まるはずがありません。このことからしても、独楽はいろいろな形で庶民の中へ広まっていったと推測されます。 このホームページの「こまの歴史」に引用した中田幸平も述べているように、日本で「こま」という名が残っている最も古い文献は「和名抄(わみょうしょう)」です。和名抄は「和名類聚抄」の略です。これは平安の中期、931〜938年にかけて編纂された和漢辞典で、分類した漢字の和名を万葉仮名で注釈したものです。その中で「独楽」の項目は鞠や双六と同じ「雑芸具」に分類され、「古末都玖利(こまつぐり)」と記されています。和名抄の「独楽」には「孔があいている」という解説がある事から、今でいう「鳴り独楽」のように空洞が空いているコマが朝鮮から伝来したものと思われます。また、和名抄の分類を見ると独楽は雑芸具(遊具)の部に入っています。遊具であれば宮廷人の中に止まるはずがありません。このことからしても、独楽はいろいろな形で庶民の中へ広まっていったと推測されます。 |
日本・朝鮮・中国の歴史の対照と独楽関連の歴史
|
 |
紀元前2000〜3500
三内丸山遺跡
紀元前1400〜2000
世界最古のコマ
(エジプト)
3世紀中頃
邪馬台国(やまたいこく)
高句麗
高麗(こま)とも呼ぶ
7世紀
日本最古の独楽
931〜938
和名抄編纂
高麗(こうらい) |
|

日本のコマの起源について話をもどしましょう。
中田幸平は『和名抄(わみょうしょう)』に記されている「古末都玖利(こまつぐり)」について、古末(こま)は他に「高麗(こま)」とも書かれ、これは中国から高麗(こま)を経て、日本に伝わったことからつけられた。また「都玖利(つぐり)」とは、こま本来の呼び名で、ツグムリともツグリともいわれ、円を意味している。ツブラにも通じている。と述べられています。
この文章で都玖利(つぐり)とは、「こま本来の呼び名」と記されている。この「こま本来の呼び名」とは、高麗(こま)から渡来してきた「こま」そのものの呼び名が都玖利(つぐリ)という意味にも解釈できるが、そうではなく、高麗から渡来する以前に日本に存在していたと思われる「こま」の呼び名が都玖利(つぐり)であったと解釈すべきです。即ち「古末都玖利(こまつぐり)」とは、高麗(こま)から渡来してきた都玖利(つぐり)ということです。(ちなみに朝鮮では独楽のことをペンイと呼ぶ)。このように解釈すると
「中国から高麗(こま)を経て渡来する以前に、既に日本にはツグリ、ツグムリ等と呼ばれる独楽の類の玩具が存在していた」ということになります。 |

元来、日本には古代に中国・朝鮮から移り住んだ人々(渡来人)がいました。古くは、弥生時代に渡来人の第一波があり、渡来人との混血化によって生まれたといわれている大陸系弥生人がいました。これらの渡来人が大陸から独楽を持って来た、或いは独楽を作る知識を持ってきた可能性があります。
何しろ古い歴史を持つ独楽の話ですから。この人々の作ったものがコマツグリ、コマツグムリなどと呼ばれるようになったことも考えられます。しかし、これよりさらに古い時代の日本にツグリ、ツグムリが存在していた可能性があるように思えるのです。 大陸系弥生人に対して、縄文人が混血化をせず狩猟社会から農耕社会へ変化した縄文系弥生人がいます。この人々やそれ以前の縄文人はコマに対する大陸の影響を受ける機会が少なかったものと思われます。以下の話は、この時代にさかのぼっての古い話です。
 皆さんは子供の時、ドングリに棒を刺して独楽のように回して遊んだ記憶はありませんか。このように独楽の原理は円いものを回して遊ぶと云う単純なものです。こんなに単純な玩具が大陸から渡来するまで日本では作られなかったと考える事自体が不自然ではないでしょうか。弥生時代(紀元前4世紀半〜紀元3世紀半)の初期は無論、縄文時代にすでに日本でも木の実や貝類、石器、土器等を工夫して、或いは木を削った独自の玩具(独楽)を作っていたと考えた方が自然ではないでしょうか。 皆さんは子供の時、ドングリに棒を刺して独楽のように回して遊んだ記憶はありませんか。このように独楽の原理は円いものを回して遊ぶと云う単純なものです。こんなに単純な玩具が大陸から渡来するまで日本では作られなかったと考える事自体が不自然ではないでしょうか。弥生時代(紀元前4世紀半〜紀元3世紀半)の初期は無論、縄文時代にすでに日本でも木の実や貝類、石器、土器等を工夫して、或いは木を削った独自の玩具(独楽)を作っていたと考えた方が自然ではないでしょうか。 |

青森県三内丸山遺跡は紀元前3500年頃〜紀元前2000年頃の縄文前期中頃から中期末にかけての遺跡です。 |
 |
復元された巨大6本柱
クリの木柱の直径は1m, 高さは14.7m。重さは1本で8トンもある。3本ずつ2列に並び、柱の間隔は4.2m。そして内側に正確に2度傾いている。 |
この遺跡には、長軸30メートル以上の巨大な建築物の跡が残されています。また直径約1メートルのクリの木柱の一部が残っています。柱の高さ14.7メートルと推定されています。このような大木を使っての巨大建造物を作るには
 |
木製の赤色の復元漆器
出土した漆器の情報をもとに製作した再現品。 |
専門的な建築・土木技術を持っていなければできない事です。また、この遺跡からは土偶や土器のほかに漆工芸品も発掘されています。右の写真のような直径25cm,厚さ5mmの赤や黒の色漆を塗った木製の椀も発掘されています。赤や黒の色漆を作りだす鉱物性の顔料を精製する技法をすでに習得していたということです。我々が想像している以上に、縄文人は色々な分野で専門的な知識を持っていたという事です。 |

以上のようなことから、縄文中期頃の人達はすでにツグリ、ツグムリなどの玩具を作る技術も遊び心も持っていたと考えたいのです。即ち縄文時代にはすでに日本でも木の実や貝類、石器、土器等を工夫して、或いは木を削った独自の玩具(ツグリ)を作っていたと推測します。 |
このように考えると日本もまた独楽発祥の地と云うことになります。
その後、時代の経過と共に、ツグリ、ツグムリ等と呼ばれていた日本独自の玩具は、渡来してきた完成度の高いコマツグリ・コマツグムリ等と呼ばれた「こま」に感化され、吸収されて、いつの間にか独楽という言葉に統一されたものと考えます。
 中国の史書「魏志倭人伝(ぎしわじんでん)」に記されている邪馬台国(やまたいこく:3世紀中頃)は、現在なお所在不明の謎の国ですが、いずれはその存在場所が解明されるでしょう。その際、その遺跡からこまが発掘されるなどという夢のような話が実現する可能性があります。そこで発掘された「こま」が渡来したものか、日本独自のものか、その当時ツグリ、ツグムリと呼ばれていたのか或いは古末都玖利(こまつぐり)等と呼ばれていたのか、また女王卑弥呼(ひみこ)が遊び道具、飾り物、占い等に使っていたのか、または庶民の遊び道具だったのか等等、想像するだけでゾクゾクします。更に遡って、三内丸山遺跡から赤や黒の漆塗りの独楽発見などとなれば、世界最古といわれているエジプトの独楽よりさらに古い独楽ということになります。そんな期待もしたくなります。 中国の史書「魏志倭人伝(ぎしわじんでん)」に記されている邪馬台国(やまたいこく:3世紀中頃)は、現在なお所在不明の謎の国ですが、いずれはその存在場所が解明されるでしょう。その際、その遺跡からこまが発掘されるなどという夢のような話が実現する可能性があります。そこで発掘された「こま」が渡来したものか、日本独自のものか、その当時ツグリ、ツグムリと呼ばれていたのか或いは古末都玖利(こまつぐり)等と呼ばれていたのか、また女王卑弥呼(ひみこ)が遊び道具、飾り物、占い等に使っていたのか、または庶民の遊び道具だったのか等等、想像するだけでゾクゾクします。更に遡って、三内丸山遺跡から赤や黒の漆塗りの独楽発見などとなれば、世界最古といわれているエジプトの独楽よりさらに古い独楽ということになります。そんな期待もしたくなります。
たかが独楽、されど独楽。独楽には夢があります。 |
|