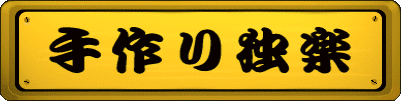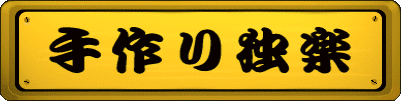益田式広告紙独楽の作り方詳細
ここでは小さい独楽と大きい独楽の2種類の作り方を紹介します。 |
| 小さい独楽の作り方 |
| 用意するもの |
| 1) |
直径10ミリ、長さ60センチ程度のプラスチック棒 |
| 2) |
壁掛け用フック:ねじ部直径2.5ミリ、長さ2センチ位のもの |
| 3) |
糊 |
| 4) |
折り込広告紙:25センチ×40センチ程度でなるべく薄いものがよい |
|
| 独楽本体の作り方 |
| 1) |
| 折り込み広告紙を机の上に広げ、プラスチック棒を対角線に平行になるように置いて端から棒を芯にして巻きつけていく。巻いた紙が緩まないように手で押さえながら棒を抜く。巻いた紙はほどけないように洗濯バサミではさんでおく。 |
|
| 2) |
| 巻いた紙の先端をフックに巻きつける。この場合紙の先端を少し水でぬらしておくとしっかりと巻きつく。空回りさせないようにフックをねじって紙を巻きつける。巻いた紙は巻きつけるにしたがって自然につぶれてくる。巻かれた紙がフックの鍔(ツバ)にかぶらないように注意する。最後まで巻ききったら改めて巻いた紙を固定して、フックを更に回転させ巻き方を固くする。 |
|
| 3) |
巻いた紙が緩まないように注意してフックを逆回転させ紙から抜いて後、紙の端を糊で固定する。 |
| 4) |
つま楊枝に糊をつけて、巻いた紙の穴に差し込む。この場合楊枝をねじりながら差し込むと扱いやすい。手を楊枝で刺さないように注意する。適当な長さまで楊枝が貫通したら楊枝の先端をハサミで切っておく。 |
 |
 |
 |
 |
 |
(1)
プラスチック棒に広告紙を斜めに巻く
|
(2)
プラスチック棒を抜いて先端をフックに巻きつける |
(3)
フックに紙を最後まで固く巻いた後、フックを逆回転して抜く |
(4)
抜いた穴に楊枝やストロー等の芯棒を差し込んで出来上がり
|
(5)
出来上がった独楽は良く回っている |
|
|
|
| 大きい独楽の作り方 |
| 1) |
大きい独楽も原理的には小さい独楽と同様の方法で作る。ねじ部の直径が8ミリ程度の大きなフックだけでも出来るが、下記のワンポイントに示した器具を使うと木材が鍔代わりとなってより簡便に綺麗な独楽が出来る。プラスチック棒も少し太いもの(直径12ミリ以上)を用いるほうがよい。あまり太いと軸を差し込むのが難しくなる。小さい独楽の時と同じように巻いていくが、巻いた紙が複数必要になるのでその数だけ用意しておく。 |
| 2) |
前の紙に次の紙をゆるまないようにはさみこんで巻いておけば糊を使わなくても大丈夫である。このように次々挟み込んで巻いていき所定の大きさになったら最後の部分を糊で固定する。糊が乾いたらフックを逆回しして巻いた紙から抜くのは小さい独楽の時と同じである。 |
| 3) |
芯棒は少し厚めの紙(10センチ×20センチ程度)のものを二本の針金をヘアピン状に曲げたものなどを芯にして独楽本体と同じく対角線に平行に巻くことによって作る。糊をつけて独楽本体に差し込むとき端が本体の穴の中に収まるようにすると軸が広がって本体に密着するとともに軸自身を糊で緩まないようにしないでも済む。 |
| 4) |
先端は巻き数が少なく弱いのでハサミで切り取っておく。
|
|
「独楽の部屋」の主が作った益田式広告紙独楽
広告紙独楽を作ってみたところ最初の2~3個は戸惑いましたが、すぐに比較的綺麗な独楽が出来るようになりました。簡単にお正月のお飾りになる程度の独楽ができました。皆様も一度作ってみたらいかがですか。
初心者の私が作った独楽をご覧ください。(右写真)→
左の2個の広告紙独楽の芯棒は広告紙で作ったもの。右の独楽の芯棒はストローを使用したものです。
|
|
|
ワンポイント
大きな独楽を作る際、壁掛け用フックに巻紙を巻きつけると鍔(ツバ)を乗り越えてしまって綺麗に巻けない事があります。益田先生の器具を参考にして作った写真のような器具があると綺麗に巻けます。①小さい木材に長めのビスをドライバーで差し込んだものと②C型クランプ(2~300円で購入可)で2枚の板の間に壁掛け用フックを挟んで固定したものです。どちらの器具でも巻紙を綺麗に力強く巻く事が出来、より簡便だと思います。また独楽の芯棒に細いストローを試みたところ簡単に出来、よく回りました。このように器具や作り方を工夫してみるのも独楽作りの楽しみの一つです。 |
 |
|
注)フックやビスの先端は怪我をしないように丸くしておくことが望ましい。 |
|